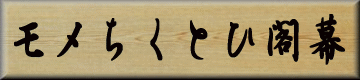 |
| 更新日 2005/03/11 |
| 3/11追加 『幕藩体制について』 |
江戸時代は、中央政府である徳川幕府が日本国の政治全般を司り、さらにその下で大名が地方政治を行う「幕藩体制」でありました。「藩」とは、今で言う都道府県単位に近いもの。各大名が幕府から所領を許され、その所領を「藩」として治める。よく間違うのは、「藩」と「国」の違い。大名は「国」を治めているもの…と思われがちだが、大名が治めるのは「藩」であって「国」ではない。あくまで「国」は土地の境界を表す単位に過ぎない。例えば、摂津の国(現在の大阪府北部と兵庫県南東部)には、高槻藩、麻田藩、尼崎藩、三田藩の4つの藩があり、それぞれ支配している大名は異なる。また、学校などで習った記憶があると思うが「徳川御三家」についても、一般的に「尾張藩、紀伊藩、水戸藩」などと呼ばれますが、厳密に言えば「名古屋藩、和歌山藩、水戸藩」となる。尾張と紀伊は国名であり、藩名でない。尾張にしても紀伊にしても、その国内に他大名が治める藩がないため、便宜的に国ごとひっくるめて「藩」扱いで呼んでいるだけのこと。そこらへんをお間違えなきよう…。 次に「藩」を治める大名について。「大名」とは、禄高1万石以上の武士で、幕府将軍と主従関係を結ぶ事によって領地を安堵される者のことを言う。また、領地安堵の交換条件として老中など幕府の要職にも就く。(ただし、例外的に蝦夷の松前藩などは実高1万石以下であっても、1万石格の大名扱いとなっている) 幕府は、大名に対して「親藩」「譜代」「外様」の別を設けている。これも学校で習ったはず。簡単に言えば、「親藩」は徳川将軍家の縁者筋の大名、「譜代」は関ヶ原合戦以前より徳川家と臣従関係にある大名、「外様」は関ヶ原合戦以降徳川家に服従した大名。幕府は、この3者を全国に上手く配置することによって300年弱もの間、幕藩体制を維持できたわけである。中央である江戸の周りを譜代藩で固め、外様藩を江戸から遠ざけ、幕府転覆を謀る不埒大名を寄せ付けぬようにするなど、なかなか考えられた支配体制である。 てことで、「ひとくち」と称してるくせに、長く書きすぎたためこれにて。 |